人生の教訓を示してくれることわざ。
英語のことわざ。さらっと言いたい!
English proverbs for your better life.

a lessonとか
a moralとか
teachingsって言うよ!
知らなかった。

- 石橋をたたいて渡るって英語で何て言うの?
- 明日の百より今日の五十、は英語で A bird in hand is worth two in the bush.
- 能ある鷹は爪かくす、は英語で Who knows most speaks least.
- 石橋をたたいて渡る、は英語で Hear twice before you speak once.
- 石の上にも三年、は英語で A rolling stone gather no moss.
- 一を聞いて、十を知る、は英語で A word is enough to the wise.
- 命あっての物種(ものだね)は英語で A living dog better than a dead lion.
- 明日は明日の風が吹く、は英語で Tomorrow is another day.
- 二兎追うもの一兎をも得ず、は英語で Between two stools you fall to the ground.
- 言うは易し、行うは難しは英語で Who will bell the cat?
- 亀の甲より年の劫、は英語で Years know more than books.
石橋をたたいて渡るって英語で何て言うの?
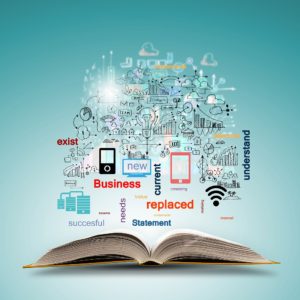
- A bird in hand is worth two in the bush.
- Who knows most speaks least.
- To knock on the stone Bridge and cross it.
- To stay for Three years on a stone.
- To hear one and realize ten.
- A living dog is better than a dead lion.
- Tomorrow is another day.
- Between two stools you fall to the ground.
- Who will bell the cat?
- Years know more than books.
明日の百より今日の五十、は英語で A bird in hand is worth two in the bush.
<直訳>Today’s fifty is worthier than tomorrow’s hundred.
手の中の一羽の鳥は茂みの中の二羽の鳥より価値がある。
将来手に入るかもしれない大きなものより、今手にできる小さなもののほうが、より確実であり、あまり欲深く考えて失敗しないことのほうが賢明である。
日本では「取らぬたぬきの皮算用」ということわざもあります。まだ、手にしてないうちから大きすぎる夢をみるのではなく、足元から一歩ずつ歩みを進めて確実に前進したいものです。英語圏でも鳥を使って表しています。これは狩猟民族の名残でしょうか。たぬきは古くから日本人にとっては身近な動物のようです。都会で生活している人にはピンと来ないかもしれません。
能ある鷹は爪かくす、は英語で Who knows most speaks least.
<直訳>A clever Hawk conceals his sharp talons.
もっとも知っているひとは口数が少ない。
本当に実力のある人は、真に必要のある場合にしかその実力を示さないものである、という意味ですね。このページを見ている人は実力のある鷹になるために努力していることがよくわかります。素晴らしい!
石橋をたたいて渡る、は英語で Hear twice before you speak once.
<直訳>To knock on the bridge and cross it.
一回話す前に二回聞け。
物事を行うときは、じっくり考えたあとでするべきであるという意味ですね。日本ではジョークで「石橋をたたきすぎて割ってしまう。」なんていうことがあります。慎重もここまでくると行きすぎです。あなたは石橋をたたいて渡るタイプですか?たたく前にわたるタイプですか?それともたたき割ってしまいますか?
英語では1回話す前に2回聞きなさいと言っています。
石の上にも三年、は英語で A rolling stone gather no moss.
<直訳>To stay for three years on a stone.
転がる石に苔生さず。
日本でも「ころがる石にこけむさず」ともいいますね。どんなこともそれなりになるには3年かかると説いています。ほんとに心にしみます。たかだか100年の限られた人生のなかで3年という貴重な時間を使って自分のキャリアを育てていくことは尊いです。涙が出そうです。

一を聞いて、十を知る、は英語で A word is enough to the wise.
<直訳>To hear one and realiza ten.
賢者には一つの言葉で十分。
一つ聞いただけで、十つまり全体のことが理解できるというのは、とても賢いということですね。一つを聞いて十を理解できるようになるためには上にあるように少なくとも3年の修行が必要なのではないでしょうか。
命あっての物種(ものだね)は英語で A living dog better than a dead lion.
<直訳>Without life, no source of things.
生きている犬は死んだライオンよりまし。
何事も命があるからこそできるのであって死んだら何もできない。つまり命を大切にしなさいと説いています。英語ではライオンがでてくるところが不思議ですね。死んでいるライオンより生きている犬のほうがマシって言うんですね。
ここで「物種(ものだね)」ってなんだろうと思った方もいるのではないでしょうか。「物種」とはものの元になるもの、物事の根本、根幹のことを表します。あまり最近は使われない言葉ですね。
明日は明日の風が吹く、は英語で Tomorrow is another day.
<直訳>The winds of tomorrow will blow tomorrow.
明日は別の日。
明日起こることを今日あれこれと思い悩んでも仕方がない。つまりなるようにしかならないという意味ですね。世の中って本当に不思議で毎日真面目に暮らしていれば、自然と流れて行ってほしい方に物事が流れていくように思います。
英語の”Tomorrow is another day.”はマーガレット・ミッチェルの有名な小説『風と共に去りぬ』の最後のシーンで主人公のスカーレットが自分に言い聞かせるようにつぶやくセリフです。
とても簡単な英語なので、いろんな場面でサラッと言ってみたいですね!

二兎追うもの一兎をも得ず、は英語で Between two stools you fall to the ground.
「虻蜂(あぶはち)取らず。」
二兎(にと)追うもの一兎(いっと)をも得ず。
<直訳>
If you try to run after a Horsefly and Bee, you will end up catching neither.
Someone who chases two rabbits can’t get even one rabbit.
2つに椅子の間で転げ落ちる。
日本では虻(あぶ)や蜂(はち)そしてウサギを取ろうとする人にたとえますが、英語では2つの椅子を取ろうとすると表現しています。2つの椅子の間から転げ落ちる様子が想像できて笑えます。
言うは易し、行うは難しは英語で Who will bell the cat?
<直訳>Saying is easy and doing is defficult.
誰がネコに鈴を付けるのだ?
これは、『イソップ童話』の中のお話にありますね。ネズミにとってネコは天敵。ネコが近くにいると安心して生活することができません。そこで、ネコの首に鈴をつければいつでもネコが近くに来たことを知ることができます。このアイディアは最高ですが、ではいったいだれがネコの首に鈴をつけるのかという大問題にぶち当たります。
”Who will bell the cat?”
言うのは簡単だけど、実行することは難しいですね。
亀の甲より年の劫、は英語で Years know more than books.
亀の甲より年の劫(かめのこうよりとしのこう)
<直訳>The older, the wiser.
年月は本より物事を知っている。
日本では亀の甲(こう)と年の劫(こう)が韻をふんでいることと、亀は長生きすることからこのような表現をします。日本語の韻というのは奥が深いですね。
日本では一万年生きる亀よりも、長い経験のある人間の方が価値があると説きます。英語では知識の宝庫である本よりも年月の方が物事を知っていると説きます。年をとることをネガティブに捉える人も多い気がしますが、年をとらないとできないことも、この世にはたくさんあると思います。年を取ったからこそ重みがある価値を大切にしたいと思います。

いかがでしたか?今日は人生の教訓に関することわざを集めてみました。比較的安易な英語で言い表せることわざが多かったので、いろいろな場面でサラッと言ってみちゃってくださいね。
では、また。
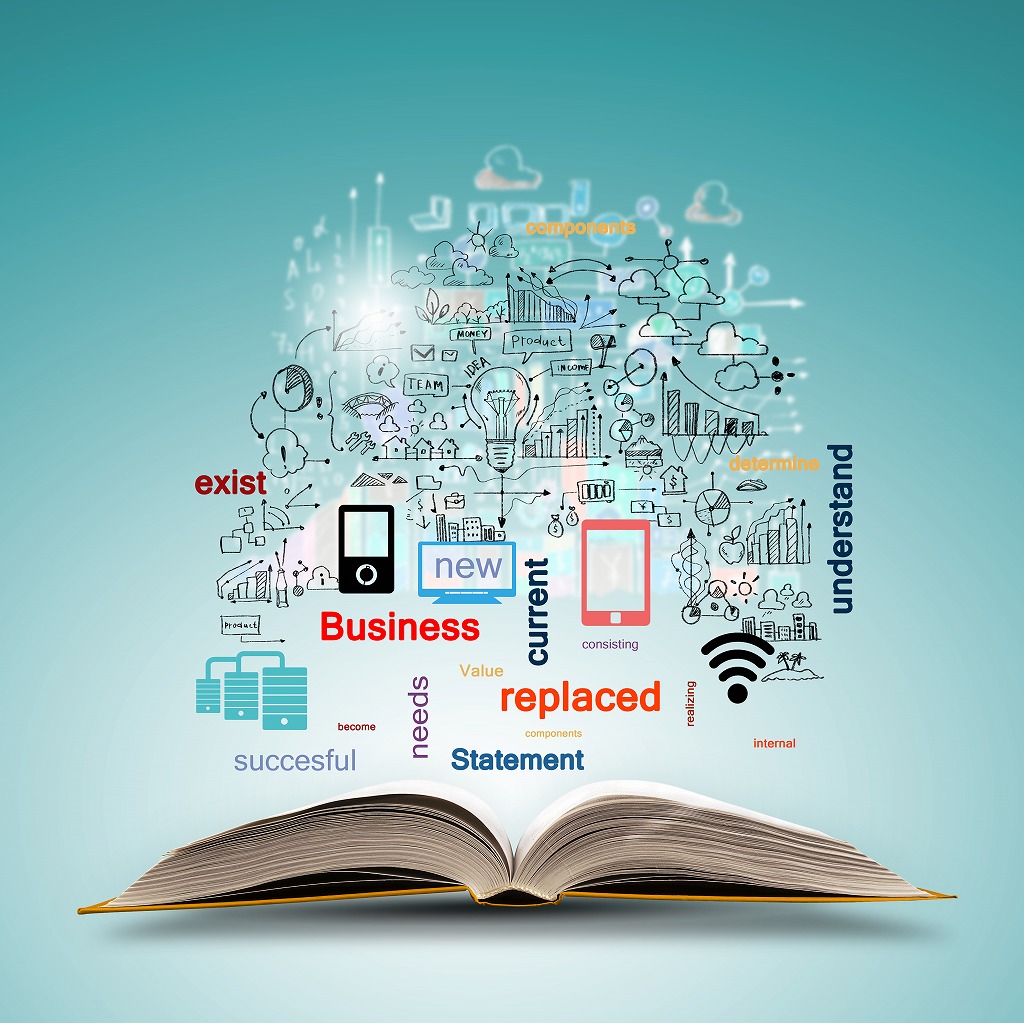


コメント